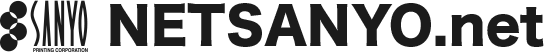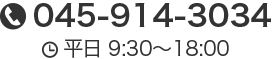デザインに取り入れたい!写真に関する5つの心理効果
デザイン
こんにちは、NET SANYOのK2です。
心理効果とデザインは密接に関わっているのをご存じでしょうか?
心理効果を踏まえたデザインやレイアウトを行うことで、ユーザーの関心を引いたり、商品のイメージを引き立たせることができます。
今回はデザインに関する心理効果や法則の中から、画像の選定や配置に生かせるものを5つご紹介いたします。
ぜひ、広告に使う写真選びなどの参考にしてみてください。
クレショフ効果
同じ画像でも、その前後の画像によって受ける印象が異なるという心理効果です。
デザインにおいても、写真の組み合わせによってあるイメージを与えたり、あるいは商品のもつイメージを際立たせることが可能です。
(例)石鹸の写真と、他の写真の組み合わせ
汚れた体も綺麗にできそうなイメージ

良い香りのしそうなイメージ

成分にこだわって開発していそうなイメージ

3Bの法則
広告業界の経験的法則です。3Bとは
- Baby(赤ちゃん)
- Beauty(美人、美しい物)
- Beast(動物)
の略。これらを取り入れたCMや広告は目を引きやすく、好感を持たれやすいというものです。
ソフトバンクのCMは、この3Bのうち2つの要素(Beauty・Beast)を取り入れています。


森永乳業の妊娠・育児情報サイト「はぐくみ」のfacebookページでは、子育てに関する情報を可愛らしい赤ちゃん(Baby)の写真とともに発信しています。

ベビーフェイス効果

人は、丸顔で大きな目・小さい鼻・短い顎・広い額などの特徴を持つ人物に「無邪気」「可愛い」「純真無垢」といった印象を持つ性質があります。
デザインで親しみやすい印象を与えたいときには、これらの特徴を持つ人物の写真を使うと効果的です。
逆に威厳を感じさせたいときには、これらの特徴から遠い人物の写真を使うと良いでしょう。
社会的証明の原理

あなたにはこんな経験はありませんか?
- 外食する際、待っている客のいないお店よりも、行列ができているお店を選んだ。
人には、他人の行動を基準にして自分の行動を決める性質があります。
広告でよく見る「売上No,1」「会員数○万人」といった表現は、この心理効果を利用しています。バラエティ番組で録音された笑い声を流す演出も、視聴者により番組を面白く感じてもらえる効果があるそうです。
この効果はデザインにも活用できます。人物の視線の先にボタンや注目させたい情報を配置することで、同じ方向にユーザーの視線を誘導することができます。
見えない部分の「理想化」

人は、見えない部分を想像で補う性質があります。
「被写体の一部を隠す」のは、特に食品でよく使われる手法です。
被写体の一部をあえて見えなくすることで、構図にダイナミックさが生まれるとともに、見えない部分を想像させることができます。
また人間の顔も、一部を隠すことで期待を生み、より魅力的に見せることができます。「マスクをしていると、より美人に見える」なんて話もたまに聞きますよね。

まとめ
心理効果の中で、写真の撮影や選定・配置に生かせるものをピックアップしてみました。いかがでしたか?
Webサイト・印刷物・SNS・動画など媒体を問わず活用することができますので、ぜひ参考になさってください。
ではでは、K2でした。
参考